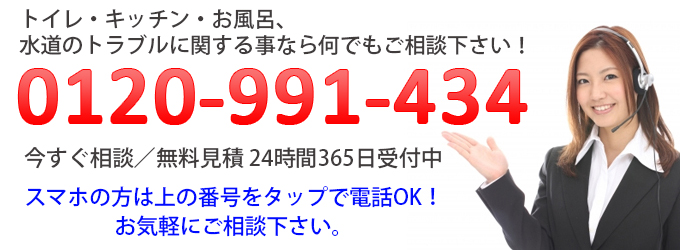家のリフォームをする際に、通常のトイレから節水トイレへ変更を検討する方も少なくありません。
節水トイレは、使用する水の量が少なくエコである点が重要視されています。
一方で、節水トイレは、「トイレがつまりやすい。」という問題が取り上げられる事もあります。
水が流れなく、トイレがつまるなどのトラブルが起こる原因や、使用上の注意点をチェックしてみましょう。
目次
節水トイレとは?
トイレを使用した後に、流す水について深く考えているという方は少ないでしょう。
10年程度前に普及した従来型のトイレの場合、大洗浄の際には、1回につき13L程度の水が必要とされていました。
最近普及している節水型トイレの場合は4.8L程度、最新式では3.8L程度で大洗浄ができるようになっています。
節水トイレに入れ替える事なく、節水できるとして、トイレのタンクの中にペットボトルやレンガ、瓶などを入れるという方もいます。
ですが、節水よりも破損の問題が大きく節水方法として不向きです。
節水トイレは実験や検査などを繰り返し、少ない水量でも汚物が流れるような技術が施されたトイレです。
節水トイレの使用は、従来型トイレよりも無駄な水の使用を減らすエコ活動になる事がメリットです。
節水トイレの効果は、一般的な家庭用のお風呂の水の量に換算して、1年間に200杯以上の水が節約できると言われています。
無駄な水道代も減るので、節水トイレは経済的な負担の面でも良いと言われています。
節水トイレは水量が少ないからつまりやすいって本当?
「節水トイレに変えた途端、トイレがつまってしまって対処に手をやいている。」
という声を耳にした事がある方もいるかもしれません。
節水トイレの1回の洗浄で流れる水の量は、従来型のトイレよりも少ない量です。
しかし、極度に水量が少ない場合を除き、節水トイレの水量がトイレのつまりの直接的な原因ではありません。
節水トイレを販売している各メーカーは、技術を結集させ、何度も様々な実験を行い製品化しています。
メーカーが想定している範囲内の使い方であれば、基本的には節水トイレの水量が原因で、トイレがつまる事は無いと捉えておいて良いでしょう。
節水トイレと従来型トイレの汚物の流し方に変わりはなく、どちらも同じ物理の法則に基づいて水を流している点もチェックしておくべきところです。
節水トイレがつまる5つの原因
節水トイレの水がつまりやすくなる原因は、おおよそ以下の5つです。
使用しているシーンを思い浮かべたときに、思い当たるものが含まれていませんか。
流したものが原因でつまる
節水トイレはトイレットペーパーや汚物が流れるように、実験結果から導きだされた水量に設定されています。
基本的には、トイレットペーパーや排泄物が適正範囲の分量であれば流れます。
ですが、便器の中に水に溶けない物や重量のある物などを落としてしまった場合、少ない水量では流し切れずにトイレがつまってしまいます。
排泄量が一般的な量よりも多い
節水トイレの水量は、一般的な排泄量で計算されています。
1回の洗浄で流す排泄量が、一般的な量よりも大幅に超えて多い場合は、トイレがつまる原因になる事があります。
トイレットペーパーの使用量が多い
節水トイレに使用する水量は、一般的に使用するトイレットペーパーの量で計算されています。
1回の洗浄で流すトイレットペーパーの量が多い場合は、トイレの詰まりの原因になる事があります。
トイレットペーパーは水にすぐ溶けるというイメージのある方が少なくありません。
ですが、使用量が多ければ多いほど、繊維が崩れる時間も長くかかってしまいます。
排水管の付着物が多い
排水管を手入れせずに使用し続けると、付着物が排水管の内側に詰まってしまっている場合があります。
排水管の内側の付着物が多ければ多いほど、トイレはつまりやすくなります。
排水管の内側のつまりが酷い場合は、水量によっては流すのが難しくなるケースが多くあります。
逆勾配になっている
水は高いところから低いところへ流れる性質があるため、排水管はゆるやかな勾配がつけられています。
しかし、地震や地盤沈下などにより勾配がなくなってしまっていたり、逆勾配、V字勾配などになってしまっているケースがあります。
勾配の角度によってトイレがつまりやすくなることは、容易に想像がつきますよね。
節水トイレを使用するときの3つの注意点
節水トイレを使用する時に守りたい3つの注意点をご紹介します。
つまりやすいと言われる節水トイレでも注意点に気をつけて、快適に使えるようにしたいですね。
決められたもの以外は流さない
トイレは決められた物以外は流さない事がポイントです。
トイレには必要でない物を持ち込まない事や、トイレの便器の上部に棚を設置しないなどの工夫で防ぐ事ができます。
排泄量が多いときには複数回に分けて流す
排泄量は、人それぞれの生活習慣や体調、体質、持病の有無などによって異なります。
排泄量が多い方の場合は、複数回に分けて流し様子を見てみましょう。
トイレットペーパーを一度で大量に使わない
トイレットペーパーの使用量に注意する事は、トイレのつまり対策に効果を発揮する可能性が高いでしょう。
・1度に使うトイレットペーパーの量を減らす。
・使用するトイレットペーパーが多い場合は途中で洗浄し、複数回に分けて流せるようにする。
などの工夫が必要です。
工夫しても節水トイレがつまってしまう場合の対処法は?
トイレが当たり前のように毎日つまってしまっては、生活に不便が生じてしまいます。
使用に関する注意を守り、節水トイレがつまらないように気を付けていても、トイレが頻繁につまって不便を感じるときには、対処に困ってしまいますよね。
どう対処すれば良いのでしょうか。
節水トイレの設定を変更する
節水トイレには一般的に、水量を設定できる機能が付いています。
試験的に節水トイレの水量の設定を増やしてみてはいかがでしょうか。
水量を増やしてしまうと節水トイレの意味が無いと思われるかもしれません。
ですが、設定を変えて水量を増やしても、従来型よりも水量は少なくて済みます。
プロの検査を受ける
前述したようにトイレのつまりの原因が、排水管内部の付着物であることも珍しくありません。
建物が古く、長く排水管の取り換え工事を行っていないケースや、経年によって排水管の内部が付着物でいっぱいになってしまっている事も考えられます。
水回りのプロに依頼し、排水管を検査してもらうのも1つの手です。
従来型のトイレに戻す
勾配や排水管の問題が原因でつまりを起こしてしまう場合は、構造から考える必要があります。
そして、排水管の取り換え工事をしなければならないケースもあります。
大規模な工事ができない場合には、節水トイレをやめて従来型のトイレに戻す事も検討してみましょう。
節水トイレの詰まりは「たうん水道修理センター」へ
節水トイレの詰まりは、従来型トイレのつまりを解消するときのようなラバーカップが有効でないケースも少なくありません。
トイレのつまりを放置することは、日常生活に支障をきたしてしまうため、すぐに対処が必要となります。
トイレのつまりに困ってしまったら、無理に自分で対処せずにプロの業者を呼ぶ方が簡単に解決する場合もあります。
神奈川県・東京都・千葉県の全域で、節水トイレのつまりにお悩みの方は、「たうん水道修理センター」へ、ご相談下さい。
豊富な実績から得たノウハウで、トイレつまりの原因をお調べし、すぐに対処させていただきます。
地域密着型の当社は時間帯を問わず、最短30分で駆けつけ、快適に生活できるように尽力させていただきます。
「節水トイレの詰まり」や「節水トイレの水漏れ」が発生した際には、ぜひ「たうん水道修理センター」に相談して下さい。
お得なWeb割キャンペーンなどもあるので、ぜひ気軽に相談してみてください。